イントロダクション
日本人が日常的に肉を食べるようになったのは、実は近代以降のことです。長い歴史の中で「肉食禁止」が続いていた日本に、なぜ明治維新を境に肉食文化が一気に広まったのでしょうか?
本記事では、奈良時代から江戸時代の肉食禁忌、明治天皇による肉食解禁、そして牛鍋や洋食文化の普及を中心に解説します。SEO対策として「明治維新」「肉食文化」「牛鍋」「文明開化」などの関連キーワードを取り入れています。
1|奈良~江戸時代:肉食禁忌の文化
日本で肉食が禁じられたのは、675年に天武天皇が「牛・馬・犬・猿・鶏」の五種の肉を禁止したことに始まります。これは仏教の影響を受けたもので、殺生を忌む思想が食習慣に直結しました。
この禁令は約1200年間続き、日本人の食文化に大きな影響を与えました(Atlas Obscura)。
江戸時代には「山鯨(猪肉)」「牡丹(鹿肉)」などの隠語を用いて、薬膳や滋養食として一部で肉が食べられていましたが、公にはタブーとされていました(Plenus 米食文化アカデミー)。
2|明治初期:明治天皇と肉食解禁
1872年(明治5年)、政府は正式に肉食を解禁します。明治天皇自身も牛肉や牛乳を摂取し、国民に西洋式食文化を受け入れるよう示しました(Nippon.com)。
この政策の背景には「文明開化」と「富国強兵」があります。欧米列強に追いつくためには、国民の体格改善と栄養補給が必要だと考えられたのです(Swarthmore University Historical Journal)。
もっとも、肉食解禁に反発する動きも強く、仏僧が皇居に乱入する事件も起きました(Atlas Obscura)。
3|文明開化と西洋化による肉食の普及
明治政府は外交儀礼でも肉料理を導入しました。1873年にはフランス料理が公式晩餐に採用され、肉や乳製品を使った料理が上流階級から広まります(Plenus 米食文化アカデミー)。
また、横浜や長崎の外国人居留地から広がった「牛鍋」が大流行しました。東京では1875年に70軒ほどだった牛鍋屋が、2年後には588軒に急増し、庶民にも肉食文化が浸透していきました(StoryStudio)。
当時は「牛鍋を食べない人は開化していない」とまで言われ、肉食が文明開化の象徴となりました。
4|牛鍋から洋食文化へ
牛鍋ブームの後、日本独自の洋食文化(Yōshoku)が生まれます。
牛丼(gyūdon)やすき焼き(sukiyaki)が大衆料理として定着し(Wikipedia)、さらに「カレーライス」「コロッケ」「トンカツ」など、日本風アレンジの洋食が国民食になっていきました(Wikipedia 洋食)。
これにより、日本の食文化は「和」と「洋」が融合するユニークな進化を遂げました。
5|和牛文化の始まりと肉食の定着
明治以前、牛は主に農耕や運搬に使われる家畜でしたが、明治以降は食用としての飼育も始まります。特に、在来種の牛と外国種を交配させたことで、今日の「和牛」のルーツが生まれました(Wikipedia Mishima cattle)。
1970年代以降、日本人の肉食習慣は急速に拡大し、牛肉や乳製品は生活に欠かせない存在となりました(Grist.org)。
6|まとめ:明治維新が変えた食の常識
明治維新による肉食解禁は、単なる食習慣の変化ではなく、日本が近代国家へと進む象徴的な出来事でした。
「牛鍋」や「洋食」は、単なる食事ではなく、日本人が文明開化を体感する場であり、同時に国力強化の一環でもあったのです。
現代の和牛や洋食文化の背景には、この明治期の大きな食文化の転換があったことを忘れてはなりません。
参考リンク一覧
Atlas Obscura: Japan’s Meat Ban
運営者について
運営者は現役AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)資格を保有するファイナンシャルプランナー。専門的な知識に基づき「ふるさと納税の選び方」「おすすめ返礼品」「節税・資産形成のポイント」を、初心者にも分かりやすく解説しています。

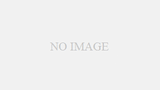
コメント